 |
 |
 |
ご祈祷は、人生の節目に伴って行われる場合と、様々な願いを叶える為に行われれる場合とがあり、主に次のようなものが挙げられます。
◆人生儀礼
初 宮 詣・・・嬰児の誕生をご神前にて奉告し、すこやかな成長を祈願します。
七五三詣・・・主に数え年3歳の男女児、5歳の男児、7歳の女児が11月15日頃ご神前に
お参りして、健やかな成長を感謝し、ますますのご加護を祈願します。
厄 払 い・・・一般的に数え年で男性25、42、61歳、女性19、33、37歳の厄年にあたる人
がご神前にて、災厄が除かれるよう祈願します。
◆諸祈願
商売繁盛・・・家業や社業の繁盛を祈願します。
家内安全・・・家と家族の平穏無事、隆昌繁栄を祈願します。
大漁満足・海上安全・・・航海の無事と豊漁を祈願します。
交通安全・・・陸上交通の安全を祈願し、お車をお祓いします。
心願成就・・・様々な願い事(心願)が叶うよう祈願します。
|
|
 |
| (1)申込 |
(2)手水-A |
(2)手水-B |
 |
 |
 |
| 祈祷受付所にて用紙に住所氏名、祈願内容等を記入します。 |
祈祷を受ける準備として心身を清める為、先ず手を洗い、 |
次に口を濯ぎ、もう一度手を洗います。 |
| (2)手水-C |
(3)参入-A |
(3)参入-B |
 |
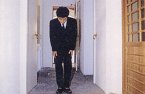 |
 |
| 最後に巫女より半紙を受け取り、手と口を拭います。 |
社殿に参入する際、軽く一礼します。 |
神職が太鼓を鳴らします。 |
| (3)参入-C |
(3)参入-D |
(4)修祓-A |
 |
 |
 |
| 心静かに待ちます。 |
斎主、祭員、巫女が所定の座に着きご祈祷が始まります。 |
祭員が祓詞を奏上します。
(起立、低頭します) |
| (4)修祓-B |
(5)献饌 |
(6)祝詞奏上-A |
 |
 |
 |
祓串にてお祓いをします。
(起立、低頭してうけます) |
巫女がご神前にお供えをします。 |
斎主がご祈祷の祝詞を奏上します。 |
| (6)祝詞奏上-B |
(7)福鈴 |
(8)拝礼-A |
 |
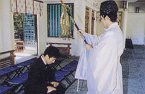 |
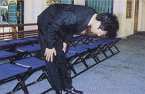 |
| その間起立、低頭します。 |
福鈴を着席のまま、低頭して受けます。 |
祭員先導のもと、ご神前に向い二礼。 |
| (8)拝礼-B |
(9)撤饌 |
(10)直会 |
 |
 |
 |
| 二拍手、一礼にて拝礼をします。 |
巫女がお供えを撤下します。 |
お下がりを受け取り、ご神酒にて直会をします。 |
|
 |
えぼし
烏帽子・・・・・・・
紙で作り黒漆で塗
り固めてあります。
初めは黒い絹で柔
らかいものでした。 |
 |
しゃく
笏・・・・・・・・・
威儀をただし、また
自己の姿勢を正す
為のものです。
貞丈雑記に「笏は
我が身の歪みを直
すべき為の定規な
り」を、あり昔は象
牙等も使われてい
ましたが、現在では
桜・櫟等の木が用い
られます。
|
 |
|
 |
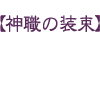 |
かりぎぬ
・・・・・狩衣
「雁衣」「猟衣」と
も書き狩猟のときに着
用し、袖口にはくっきり
紐が通っていてしぼる
ことができ、「布衣(ほ
い)」とも言います。 |
 |
あさぐつ
・・・・・浅沓
桐材をくりぬいて作り
漆で黒く塗ってありま
す。初めは皮製の黒
漆塗りのものでした。 |
 |
|
|
|
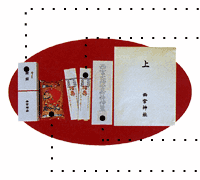 |
煎餅(お召し上がり下さい)
お箸(お使い下さい) |
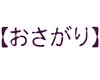 |
お札(清浄な場所にお祀り下さい)
お米(お召し上がり下さい) |
|
|
|
|
|







